導入実績
さまざまな企業・団体・分野で
SOBAの技術が活用されています。
Seminarセミナー
株式会社京都リサーチパーク
2016年4月20日に開催された「再生医療サポートビジネス懇話会」(主催:京都リサーチパーク㈱ 技術協力:㈱SOBAプロジェクト) にて、京都と東京間で 「ミエルカ・クラウド」をご利用いただきセミナーの配信を行いました。 音声はワイヤレスマイクからラインでPCに取り込み、パワーポイントと先生の姿を広角カメラで映しました。


「Google Developer Day Japan」
2010年9月28日に開催された「Google Developer Day 2010 Japan」のイベント(主催:Google、協賛:株式会社SOBAプロジェクト、UQコミュニケーションズ株式会社)で、同年3月11日のイベントに続いて、東京メイン会場(東京国際フォーラム)と京都サテライト会場(京都リサーチパーク)をつなぐ中継システムとして、SOBA mierukaをご利用いただきました。 京都では200名以上が参加しました。

「Google DevFest Japan」
2010年3月11日に開催された「Google DevFest 2010 Japan」のイベント(主催:Google、協賛:株式会社SOBAプロジェクト、UQコミュニケーションズ株式会社)で、セミナー会場間の中継に SOBA mieruka をご利用いただきました。 メイン会場となるベルサール汐留とサテライト会場である京都リサーチパーク(参加者約100名)の2拠点間をつなぎ、国内外のエンジニアや開発者コミュニティによる講演やセミナーを通じて、最新の技術等について活発な交流が行われました。 ※「基調講演: Google DevFest 2010 Japan」ビデオ(43:57)では、途中東京会場からの呼びかけに対して、京都会場からSOBA mierukaで応答している様子(37:00~39:00の2分程)がご覧になれます。
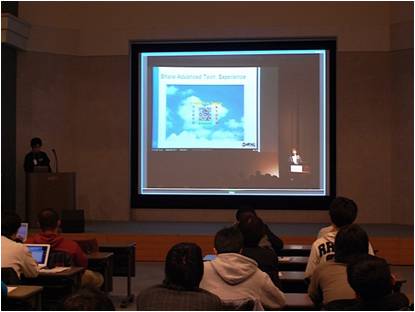
Education教育
長崎県立鳴滝高等学校通信制
長崎県立鳴滝高等学校通信制課程では、対馬、壱岐、五島など通学が難しい生徒のために各島の通信制協力校の教室を借りて、本校と離島の各教室をつないだ遠隔授業を5年にわたり実践研究されてきました。2012年度より遠隔授業のシステムとしてSOBA mieruka を正式に採用いただきました。
福島県教育センター
福島県では県教育センターが中心となり、県内の公立学校へのネットワークサービスの一つとしてWeb会議システムの独自導入を計画し、2011年にSOBA mieruka を採用いただきました。なお導入に先立ち、 2009年~2011年福島県教育委員会の中山間地域連携事業において、中山間地域の複数の小学校をSOBA mieruka でつなぎ、ALT(外国語指導助手)による英語の合同交流授業等が行われ、中山間地域の児童の学習意欲の向上や指導教師の指導力向上に取り組まれました。学校間の交流授業、ライブ授業の参観・指導助言、本校/サテライト校の職員会や担当教員打合せ等幅広い用途で、福島県版SOBA mierukaが活用されています。
京都工芸繊維大学・(財)京都高度技術研究所
財団法人京都高度技術研究所/京都工芸繊維大学ベンチャーラボラトリー
京都高度技術研究所内で会委細されたMOT(技術経営)研修を、京都工芸繊維大学大学院にライブ中継し、講堂で大学院生120名以上が受講しました。この遠隔教育は、2006年の大学院の履修単位として認定される教育プログラムの一環として取り組まれました。
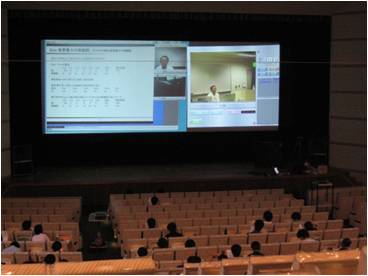
Eventイベント
財)横浜企業経営支援財団
宇宙交信イベント(日本宇宙少年団 様)
日本宇宙少年団(YAC)主催の宇宙交信イベントに、2011年、2012年と2年にわたりSOBA mieruka をご利用いただきました。このイベントは国際宇宙ステーション(ISS)に長期滞在する日本人宇宙飛行士と日本国内数か所の各会場に集まった子供たちが直接交信・会話し、宇宙のホンモノを身近に感じてもらう教育イベントです。NASAからの映像が筑波宇宙センター(JAXA)に届き、そのJAXAと国内3~4 会場間をSOBA mierukaで中継しましたが、限られた交信時間の中、ほんの数秒のタイムラグだけで、高品質な映像と音声でスムーズに交流することができ、イベントは大成功でした。

(株)東京穀物商品取引所
「2007年春季市況講演会」
2007年2月26日に開催された「春季市況講演会」で、メイン会場(東京穀物商品取引所内会議室)の講演会の様子を、サテライト会場(大阪第一ホテル)にSOBA mierukaでライブ配信しました。

Meeting会議
【1〜5人での導入例】
D社(ペットフードの製造・販売)
「特にすぐに必要としていたわけではないのですが、 Web会議システムのようなものが将来的に必要になるという認識はあり、新聞でSOBA mierukaを知り、簡単に導入できるということで導入を決めました。毎回PCでソフトを立ち上げて機器を繋いでというのが面倒だという人もいますが、弊社では毎日事務処理のミーティングで利用しています。 」(ご担当者談)
【6〜9人での導入例】
サムシングホールディングス株式会社(住宅地盤調査・改良・保証事業)
「現在、定例の役員会議、支店会議、部単位のミーティングなどで利用しています。SOBA mierukaを導入することで、いままで会議に参加できなかった遠隔地の人を含めた会議ができるようになりました。最近は会議やミーティングだけでなく、勉強会などに使うこともあります。」(管理本部ご担当者談)
【10人〜での導入例】
株式会社エネサンスホールディングス (LPガス・ガス関連器具)
「グループ会社が北海道から九州まであり、導入前は何か問題が持ち上がった際に担当者がその場所まで行って打ち合わせをしていました。移動時間縮小、交通費削減などのため、導入することに決めました。東京の会議室は広くて、最初導入した機器では全員の会話を収音できず困りましたが、SOBAにサポートしてもらい機材を変えて今は問題なく利用しています。これからも打合せ、勉強会、研修など様々な用途で利用していきたいと思っています。」(総務部 松野一夫様談)
【その他の導入例】
日新電子工業株式会社(金属機械)
「導入前は毎月、全国11拠点から各担当が集まって営業会議や製造と販売の会議をしていました。導入当初は使い方に慣れず、事前の準備等もせずカメラの前で報告事項を読み上げるくらいでしたが、最近では事前にレジュメを準備し、資料を共有しながら会議を進めています。導入から1年半くらい経ちますが、既に数百万円の経費削減になったのではないでしょうか。今後は工場と営業の間での個別のやり取りなどにも積極に利用していきたいと考えています。」(工場長 佐藤壯司様談)
某 独立行政法人(住宅地盤調査・改良・保証事業)
「現在、定例の役員会議、支店会議、部単位のミーティングなどで利用しています。SOBA mierukaを導入することで、いままで会議に参加できなかった遠隔地の人を含めた会議ができるようになりました。最近は会議やミーティングだけでなく、勉強会などに使うこともあります。」(管理本部ご担当者談)
B社(金属加工)
「導入前は毎週本社の岩国工場に岡山工場、下松工場、 姫路営業所、上海事務所から営業が集まり全社会議を行っていましたが、 移動時間や経費の問題もあり、SOBA mierukaを導入することにしました。導入した感想ですが、電話と違いWeb会議なので課金もなく長時間の会議ができるのがありがたいです。画面上で相手の顔を見ながら資料共有できるので、 本当の会議にとても近い状態で会議ができると思います。現在は毎週の全社会議以外に、突発的な会議やコンピューター操作の研修などでも活用しています。 」(ご担当者談)
C社(医薬品・化粧品の製造・販売)
「東京に本社、静岡県に工場(3か所)間で、頻繁に会議、打合せが行われているのですが、比較的軽い内容の打合せのために移動をするのは時間と費用の無駄との考えがありました。電話会議では資料を事前に配布しておく手間がかかることもあり SOBA mierukaの導入を決めました。現在は規制関係の会議で定期的に使用しています。最初はVISMEEを利用しましたが、 回線が不安定なためSOBA mierukaに変更しました。現状は問題なく利用できています。利用時間を気にしないで済むのはありがたいです。当社はパソコン操作に慣れていない人も多いため、インストール手順なども含めてITレベルの低い人向けのマニュアルがあると助かります。今後は国内、海外の業界団体、代理店との打合せに利用したいと考えています。また、英語版のマニュアルがあると助かります。」(ご担当者談)
株式会社池下設計 (建築設計・監理・施工図・施工管理)
「以前は全国6拠点の支店長が本社へ出張で集まり会議を行なっていました。出張等の経費抑制や移動による営業機会損失減を目指してWeb会議のSOBA mierukaを導入することにしました。当初Web会議ということで実効性への疑問やWeb会議機器の選定や設定の不具合などがありました。会議の回数を重ねることで実効性への疑問を解消し、機器の選定見直しや経験値による機器設定でWeb会議を実施しています。特にアプリケーション共有による会議資料の相互操作は会議の中心になるものです。今後は運用面についても支店会議のみではなく支店間同士の図面打合せなどにも活用したいと考えています。」(事業本部ご担当者談)
三共精機株式会社(機械工具商社)
「京都・滋賀・岡山の3拠点をつないで毎朝の朝礼や社内企画会議等で利用しています。集まってやる会議は、集まってやる。顔を合わせ話し合うことに勝るものはありません。“会う”と “会わない”間のコミュニケーションを創出し常日頃から育んでゆく・・・この“0.5のコミュニケーション”が今までにない社内の活性化を生み、何か新しい価値創造のきっかけになる。導入の目的は、コスト削減というよりは投資、と考えています。」(役員様談)
株式会社サンペックス
(フードサービス向けユニフォームや介護衣の企画・製造・販売)
「熊谷本社・東京支社・大阪営業所・北海道営業所・九州営業所・物流センターの6拠点に導入し、必要があればいつでもすぐに使えるようにしています。定期的に営業会議を行っていますが、軽い打ち合わせ程度の小さな会議は出張せずにSOBA mierukaを使って行う、重要な会議は今までどおり一堂に会してやる、というのが基本方針です。年5回開催していた会議が3回にでも減らせれば十分導入した価値はあるし、自分自身も移動しなくて済むので時間的・体力的にも楽です。」(役員様談)
株式会社JMRサイエンス
「東京と大阪に拠点があり、合同で会議をしたいということになり、 SOBA mierukaを導入しました。Web会議でもしっかりとコミュニケーションが取ることができ、問題なく利用しています。今後はインタビュー調査などの可能性を検討したいと考えています。 」(ご担当者談)
梱包資材販売会社 T社
「これまでは社長が各営業所を回り営業所間での会議をしていたのですが、時間を取ることが難しくなったのでSOBA mierukaを導入しました。時間短縮だけでなく交通費などの経費削減にもなり、満足して使っています。既に少し始めていますが、今後は会議だけでなく、新人研修や勉強会などでも使っていきたいと思っています。」(ご担当者談)
株式会社三ツ矢
「他の拠点との会議をする際に以前は集まっていたのですが、交通費など、会議費用をコストダウンするためにSOBA mierukaを導入しました。特に問題なく利用しており、おおむね満足しております。最近では会議以外に週1回、社内の英語教室でも利用しています」(総務部ご担当者談)
山一電機株式会社(半導体ソケット・コネクタ類の製造)
「以前、自社構築のサーバーで他社のシステムを使っていましたが、トラブルが多く、保障切れのタイミングでSOBA mierukaに切り替えました。現在は、国内だけでなく、海外(中国、フィリピン)との会議、勉強会などで利用しています。」(業務管理部ご担当者談)
Development開発実績
声優e-ラーニングシステム「SPOT」
SPOTはアニメ「サザエさん」の磯野ワカメ役や「ドラえもん」の源静香役を務めた、レジェンド声優・野村道子が3年前に「家が遠くて通えないという声が多く、ならば自宅で声優の勉強ができるオンラインの学校ができれば」と各事務所社長に相談したのが契機となり、賛同した声優プロダクション4社が垣根を超えて共同参画しました。
弊社SOBAプロジェクトは各事務所の方々と念入りに仕様を考え、web会議システムの長年の実績を活かしてSPOTのシステムを開発しております。
昨今の情勢からオンライン上でのミーティングやラーニングシステムが注目されています。弊社は2001年の産学官プロジェクトから新たなネットワーク社会の到来を予見し、独自のフレームワークを開発しweb会議システムやオンラインラーニングシステムを提供して参りました。
面接システム
多数の応募者の面接を行う企業にとって、 面接場所の確保やスケジュール調整などに費やす手間とコストの削減は大きな課題となっている。一方応募者にとっても、面接地が遠方であれば移動のための時間や費用の負担は小さくない。面接をWeb上で行うことで、面接官と応募者はお互いの顔を見ながら遠隔地であることを意識することなく対話することが可能となり、双方の利便性を高めつつ効率的に、かつ、数多くの面接を実施できるようになった。
通訳システム
スマートフォンやタブレットなど、可搬型の汎用的な端末にアプリケーションをインストールすることで、通訳システムを利用できるようになる。たとえば、ユーザが物品を購入したいが店舗にてユーザが話す外国語が通じず困った際に、スマフォやタブレットに話しかけると、遠隔地のセンターにいる通訳者が通訳を行い、店舗の担当者に伝えることで物品をスムーズに購入することができる。
電子商取引+ビジュアルコミュニケーション・システム
電子商取引ができるWebサイト(クリックして物品を購入するサイト)に、ビジュアルコミュニケーションの機能を組み込み、たとえば商品の説明を直接担当者と対話しながら聞くことができる。場合によって担当者は、商品の詳しい画像や動画などを見せながらリアルタイムにユーザに説明を行うことができる。
介護システム
介護施設の個室に端末が設置されており、その端末にはカメラやマイク・スピーカが接続されている。介護施設のセンターで多数の個室の様子をモニタリングすることができる。個室のいずれかを詳細に見たい場合には、その個室の映像が拡大され、詳細な状況を見ることができる。センター側から個室のユーザに対して話しかけることもできる。
手話通訳システム
PCやスマートフォン・タブレット上で手話通訳を行うシステム。聴者・ろう者・手話通訳者がお互いの顔や手話をみながらリアルタイムに対話することができる。聴者は手話通訳者と音声を使って話をし、ろう者は手話通訳者と手話で話をする。
デジタル掲示板システム
情報を共有したい複数の駅に設置されており、たとえば1つの駅で何か問題が発生した場合に、デジタル掲示板に書き込むと、他の複数の駅のデジタル掲示板にも瞬時に反映され、情報を共有することができる。どの駅のデジタル掲示板に書き込みを行っても、ほかの駅のデジタル掲示板に反映される。
家庭教師システム
授業を受けたい生徒は、Webサイトから自分が希望する講師を選び、家庭教師の予約を行う。生徒は、その予約した時間にWebサイトにログインすることで、家庭教師を受けることができる。PCには、顔を写すカメラとノートを写す書画カメラの2台のカメラを接続し、たとえばノートで問題を解きながら家庭教師を受けることができる。
遠隔医療システム
病院にいる医者が、自宅にいる患者を診察することができる。専用の端末を用いる。その端末には、バイタルセンサー(血圧計・心電計・体組成計・血糖値計)が接続できるようになっており、患者は毎日自分の健康状態を測定する。測定したデータはインターネットを介して自動的に病院のセンターにあるサーバにアップロードされる。診察は1週間に1回行うが、医者と患者は、このバイタルセンサーで取得したデータをお互いに見ながら、医者が診察を行う。
お見合いシステム
会員登録している男性・女性がWebサイトにログインし、そのWebサイト内でお見合いを行うことができる。たとえば、男性が女性を5人選択し、10分ずつ女性と会話することができ、最後に好みの女性を1人選んで、その1人とは長く会話を行うことができる。これら一連の処理が自動化されている。
賃貸物件販売システム
無人の場所(たとえば駅の中)にKIOSK端末のような端末を設置し、その前に来たユーザー(賃貸物件を借りたい人)に対し、遠隔地の不動産店舗にいる担当者が賃貸物件を販売する。販売の手順は、店舗と同様。ユーザーは、操作する必要がなく、担当者が物件カード・外観図・路線図・地図などを見せながら商談を進める。 最終的には、賃貸物件を実際に見に行く必要があるため、端末の前では最後に来店予約をしてもらって終了する。
詳細な開発事例は、SOBAフレームワーク・クラウドの事例でご覧いただけます。


